大学生の皆さんが避けては通れないのが「卒論」です。
ただ、卒論に対して苦手意識があったり、やる気が出なかったりする人もいるかもしれません。
実は卒論作成をとおして、学べることは多いです。
せっかく取り組むなら、真面目に取り組むのがおすすめ。
- 【卒論で身につく力】卒論で得られるものとは?
- 卒論に力を入れるメリット
そこで今回は、卒論作成を真剣に行うことで身につく力と得られるものを紹介します。
これから卒論を控えている大学生は、ぜひ卒論にも力を注いでみてくださいね。
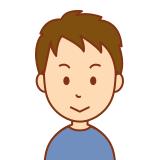
卒論で学んだことは卒業後も役立ちます。
【卒論で身につく力】卒論で得られるものとは?

卒論を面倒だと考えている大学生は多いですが、大学を卒業してみると卒論に力を入れていて良かったと思える場面が多いです。
そこでここからは、卒論で身につく力について解説します。
自分で物事を考える力
卒論作成に一生懸命取り組むことで、「自分で物事を考える力」が身につきます。
卒論では、自分なりの主張をすることが必須です。
自分の意見が反映されていない卒論は盗作とみなされるため、自分の主張を根拠立てて説明しなければいけません。
また、卒論を作成するときには自分で考えなければいけない場面も多いです。
具体的な場面でいうと主に以下のような場面が考えられます!
- 卒論で一番言いたい主張の決定
- 卒論のテーマ決定
- 卒論の資料選択
- 卒論の構成
- 卒論に関するゼミでの活動など
このように、卒論を完成させるまでは、自分で考えて選択しなければいけない場面が多いです。
この自分で考える力は、大学を卒業した先の進路でも役立ちます。
卒論作成をとおして、大学生のうちに身につけておきましょう。
論理的思考力
卒論の作成に一生懸命取り組むことで、「論理的思考力」を身につけることが可能です。
論理的思考力とは、ある結論に向けて順序立てて説明する力のことをいいます。
もしくは、物事に道筋を立てて考えることができる力ともいえますね。
卒論を作成するときは、自分の主張を論理立てて説明するために構成を考えなければいけません。
序論・本論・結論をどのような内容にするか、どの資料を引用して自分の説に説得力を持たせるかを考えることが大事です。
このように、卒論の作成に一生懸命取り組むということは、論理的思考の訓練にもなっています。
卒論を作成している最中はは意識しないと思いますが、大学を卒業してから振り返ると卒論で身につけた論理的思考力のありがたさに気づきます。
例えば、会社でのプレゼンや友だちとの会話なんかでも、論理立てて話さなければ相手が理解できない内容になってしまいます。
また、自分の主張の根拠が乏しい場合も、相手を説得するのは難しいでしょう。
このように、卒論の作成で身につけられる論理的思考力は、大学卒業後の進路にも役立てることができるスキルです。
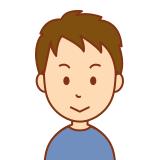
論理的思考力はあって損はないスキルです。
分かりやすい文章を書く力
卒論の作成に一生懸命取り組むことで、「分かりやすい文章を書く力」が身につきます。
卒論はだいたい2万字以上の長文を書く必要があり、人生で経験したことのないくらい文章を読み書きする経験をします。
いやでもたくさんの文章に触れますし、論文のような堅苦しいテキストにも慣れるでしょう。
そのため、文章を書くのが苦手な人でも、継続して文章作成をしていると慣れてきてうまくなります。
分かりやすい文章が書ける力は、報告書・プレゼン資料・社内資料の作成など、社会人になっても役立つスキルです。
卒論をとおして、分かりやすい文章が書ける力を身につけましょう。
卒論に力を入れるメリット

卒論を適当に書いて卒業する人もいれば、一生懸命時間をかけて作成する人もいます。
ただ、一生懸命卒論を作成した人は何かしら得るものがあるんです。
そこでここからは、卒論に力を入れるメリットを解説します。
就活でアピールできる
卒論に力を入れることで、就活でアピールすることができます。
就活では「大学生活で力を入れてきたことは?」といった質問通称「ガクチカ」を聞かれることが多いです。
ガクチカは、サークル・部活動・アルバイト・留学など力を入れたことなら当てはまり、そのなかに卒論も含まれます。
企業はガクチカでやってきたことが知りたいわけではなく、活動のなかで学んだことや人となりをチェックしています。
そのため、卒論に力を入れた理由や、卒論提出までにどういった研究をするのか分かりやすく説明できれば、企業側にアピールできます。
卒論の内容を説明するときは、企業に分かりやすく専門知識はかみ砕いて説明するのがおすすめです。
そうすることで、専門分野の研究でも企業側がイメージしやすくなりますよ。
社会人になってから文章作成スキルが活かせる
卒論作成で培った文章作成スキルは、社会人になっても活かせます。
例えば、社会人になるとメールや書類作成など、文章を作成しなければいけない場面も多いです。
日本人であれば、ほとんどの人が文章を書けますが、読み手が分かりやすい文章を書くにはポイントを押さえる能力が求められます。
結論を最初に書いたり、適度に行間を入れて読みやすくしたりすれば、読み手がストレスなく文章を読めますよね。
何気ないスキルではありますが、どんな仕事をしても大なり小なり文章作成の機会はあります。
大学生のうちに文章作成スキルを身につけておけば、社会人になってから楽です。
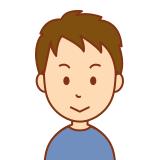
僕も文章スキルを活かして、こうしたブログを書いています。
データの大切さや活用方法が学べる
卒論作成をとおして、データの大切さや活用方法を学べます。
卒論では、原文や論文など一次資料や、書籍など二次資料を使って文章を作成します。
このとき、資料の引用方法や資料を使った論理的な説明方法が学べるのです。
社会人になると、論文や原文を使用する機会は多くありません。
しかし、論理的に説明するために資料を使うケースはあります。
例えば、プレゼンテーションをするとき、集めたデータを使って新しいアイデアを説明する場面もありますよね。
資料を適切に使って説明できれば、クライアントに意図やメリットが伝わりやすく、結果的にプレゼンテーションの成功につながるのです。
卒論を書いていると、著作権や引用などのルールも身につくので、ぜひ力を入れてほしいですね。
卒論作成で身につく力【まとめ】
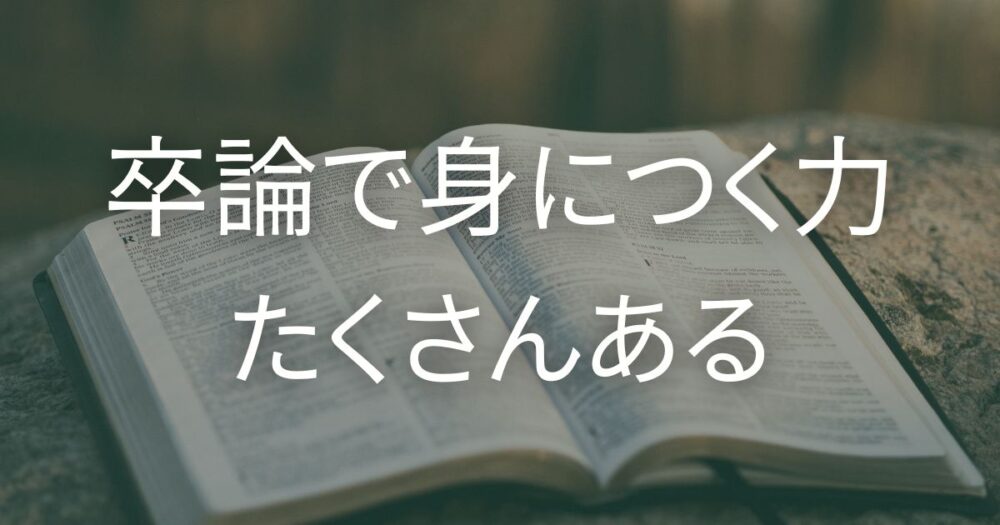
今回は、卒論の作成に一生懸命取り組むことで身につけられる力について紹介してきました。
卒論は文字数も多いですし、さまざまな決まりを守って執筆しないといけないため労力がかかります。
ただ、しっかりと取り組むことができれば、身につけられる力もたくさんあります。
皆さんも卒論を適当に作成するのではなく、少し時間を割いて卒論に取り組んでみてください。
\電子書籍を活用した情報収集もおすすめ/
卒論の準備に書籍を読みこむ人も多いですよね。
最近だと下記のような電子書籍で、タブレット・スマホなどで本が読めます。
- Kindle Unlimited
:約200万冊以上が読み放題
- audiobook.jp
 :耳で聞ける書籍が充実
:耳で聞ける書籍が充実 - Audible
:作業しながら聴く読書ができる
上記のサービスはスマホやタブレットで書籍を読む、音として聴くことができます。
卒論に必要な書籍も読めるので、図書館で貸し出し中の本も見つけられるかも!

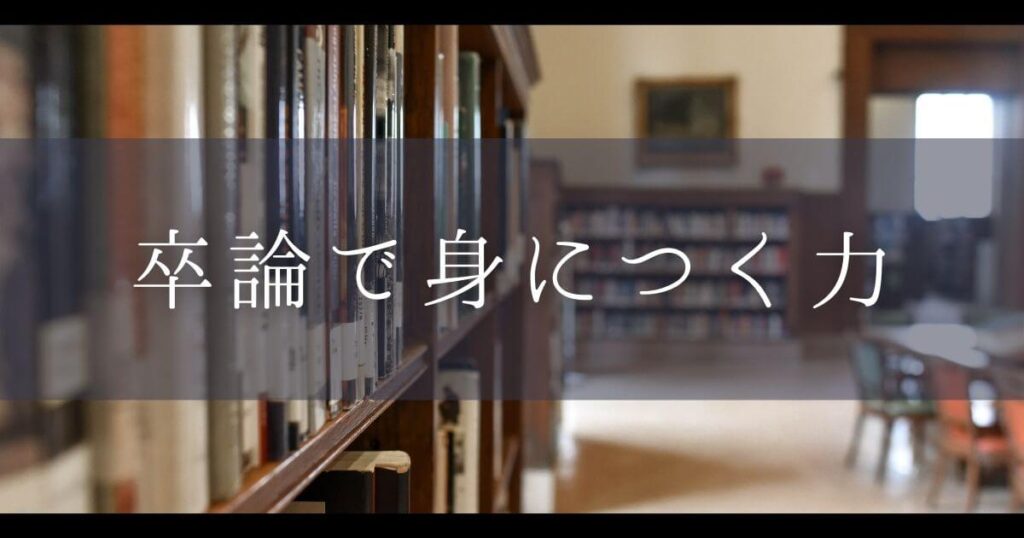
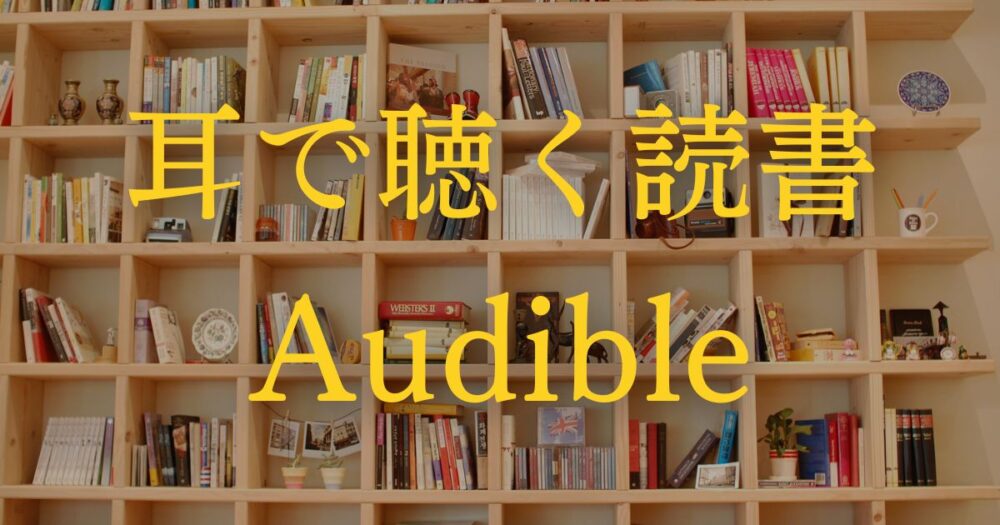

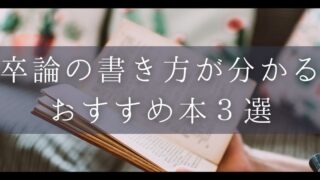
✓文系4年制大学卒
✓文系大学からIT企業に就職
✓現在フリーランス
就活情報を中心にブログ投稿をしています。
ライティング依頼・レビュー依頼のご相談はお問合せフォームまで。