卒論を問題なく完成させるには、卒論の構成をしっかりと考える必要があります。
卒論の構成は「序論・本論・結論」で考えるのが一般的。
ただ、構成の考え方がよく分からない人もいるでしょう。
そこで今回は、卒論の構成の基本である序論・本論・結論とは何を書くのかを解説します。
- 序論は先行研究や本卒論で述べることを記載
- 本論は自分が伝えたい主題を根拠と合わせて解説
- 結論は卒論全体を総括するまとめの役割

卒論構成を考えるときの参考にしてくださいね。
卒論の構成の基本【序論・本論・結論】とは?
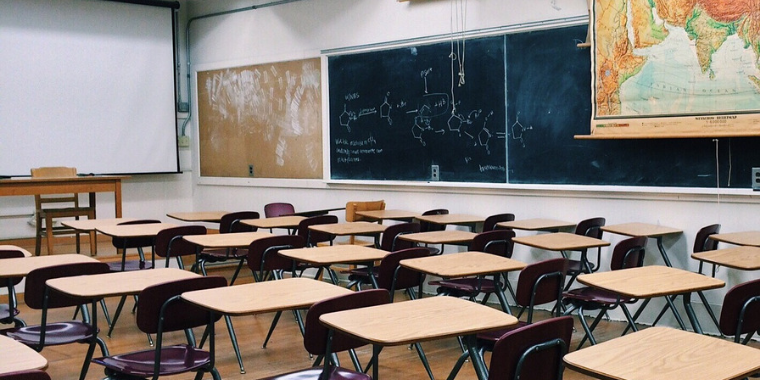
卒論の構成を考えるうえで、まず知っておきたい知識として「序論・本論・結論」があります。
構成の考え方を知ることで、かなり卒論の完成度が変わるんです。
ここでは、卒論の構成を考えるうえで大切な「序論・本論・結論」について解説していきます。
【序論】= 先行研究や卒論の内容を簡単にまとめる
卒論構成の中で「序論」もしくは「はじめに」といわれる部分は、先行研究の確認や論文での問題提起を行うところです。
どんな卒論テーマを選んだとしても、先行研究が少なからずあるはずです。
序論では、先行研究の意見を紹介しつつ、いまだに解決されていない課題を明確にしていきます。
その後、課題を解決するための方向性を提示。
本論で論証していく内容を、簡単に解説していきます。
序論をしっかりと作成することで、本論で解説する内容が分かりやすいです。
また、自分が卒論で何を明らかにしていくのか明確にできます。

序論は論文の内容を示す大事な箇所です。
【本論】= 自分が一番伝えたいことを根拠を示して説明
卒論構成の「本論」とは、自分が一番伝えたいことを根拠を示しながら説明するところです。
本論は卒論の中で最も大切な部分です。
本論の内容で卒論の評価が決まるといっても過言ではありません。
本論では事前に収集した書籍や論文などを引用しながら、自分が証明したい内容の根拠を示していく必要があります。
盗作にならないよう、自分の意見と根拠となる資料はきっちり分けて表現することが大切です。
ちなみに、引用する資料は1つの資料を引用するよりも、2つ以上の資料を引用した方が説得力が増します。
1人の専門家が正しいというものより、10人が正しいというものの方が説得力がありますよね。
卒論で引用する資料でも同じです。
なるべく多くの資料を扱った方が説得力のある文章になります。
ただ、あまりに多く資料を使うと分かりにくくなる可能性も。
バランスには注意する必要はありますね。
ちなみに、資料の探し方についてはこちらの記事で詳しく説明しているのでぜひ、参考にしてみてください。
【結論】= 最後に卒論の全体を総括
卒論の構成の中で「結論」の役割は、最後に卒論の全体を総括することです。
序論・本論で自分の意見を説明しているので、結論では今までの総括を簡単にまとめます。
また、結論では、自分の卒論では証明しきれなかった部分(今後の課題)も説明します。
1つの論文の中で、今まであった問題(課題)をすべて解決することは不可能です。
論文では、自分が決めた争点に絞って課題を解決するため、それ以外のポイントは他の人に解決を任せることになります。
そのため結論では、自分が証明したことを明確にしつつ、今後の研究に期待したいところを記載するのです。

結論を分かりやすくまとめると、全体の印象がよくなりますよ。
卒論の構成を考えるときのポイント
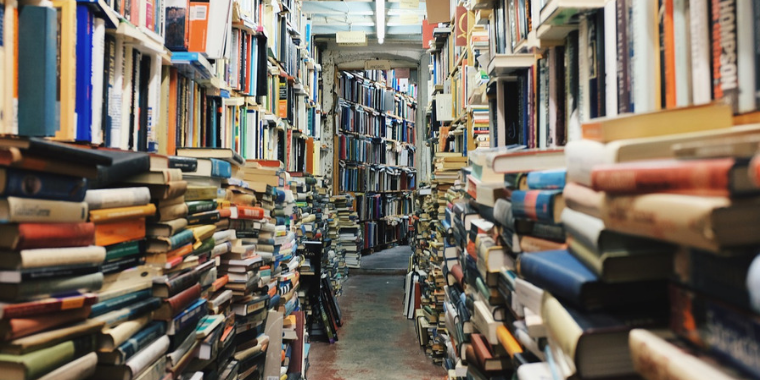
卒論の構成の基本となる「序論・本論・結論」が分かったところで、実際に構成を考えるときのコツも知りたいですよね。
そこでここからは、卒論の構成を考えるときのポイントをご紹介していきます。
卒論で自分が解明したいことを明確にする
卒論の構成を考えるポイントとして、卒論で自分が解明したいことを明確にしておくことが挙げられます。
よくありがちなミスとして、いきなり卒論の構成を考え始めるということがあります。
しかし、これでは全体で内容がばらつきやすいです!
卒論の構成を考えるときには、まず卒論の中で一番言いたいことをまとめましょう。
そのうえで、序論・本論・結論で大まかに何を書いていくかまとめることをおすすめします。
大まかに内容をまとめたうえで、詳しい項目を決めていくと良いでしょう。
本論に説得力を持たせる資料を探しておく
卒論の構成を考える前に、本論に説得力を持たせられる資料を探しておく必要があります。
せっかく序論・本論・結論で書くことを決めても、自分の主張を証明できる資料がなければ卒論として成立しません。
また、資料がないと本論の中身がスカスカで、自分の意見に説得力を持たせることが難しいです。
そのため、事前に自分の意見を証明できる資料をしっかりと集めておくことが大事になります。
説得力を持たせる資料は、大学図書館にある書籍文献・論文などの二次文献、原本といわれる一次資料があります。
卒論の構成を考える前に、一次資料を含む根拠となる資料を集めるようにしてください!
序論・本論・結論で矛盾がないようにする
卒論の構成を考えるときのポイントとして、序論・本論・結論で主張している内容が矛盾しないようにすることが大切です。
卒論では、全体を通して主張が同じである必要があります。
しかし、卒論は平均2万字は書かないといけないため、書いている間に主張が変わってしまうケースも少なくありません。
そのため、卒論全体をとおして主張が変わらないように、主張すべき内容をメモすることが大事です。
卒論の構成はしっかり考えよう【まとめ】
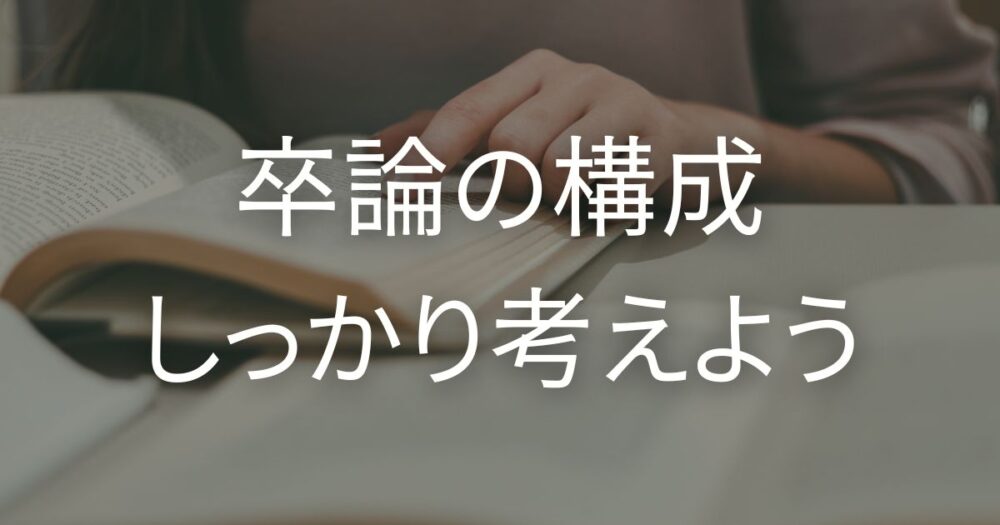
今回は、卒論の構成である序論・本論・結論について解説しました。
卒論を作成するときには、序論・本論・結論の構成を意識することが大事です。
構成をしっかり作成しておけば、卒論を書き始めてからも書きやすくなります。
卒論でどんなことを書けばいいのか理解したうえで、しっかりと卒論を作成していきましょう。
\電子書籍を活用した情報収集もおすすめ/
卒論の準備に書籍を読みこむ人も多いですよね。
最近だと下記のような電子書籍で、タブレット・スマホなどで本が読めます。
- Kindle Unlimited
:約200万冊以上が読み放題
- audiobook.jp
 :耳で聞ける書籍が充実
:耳で聞ける書籍が充実 - Audible
:作業しながら聴く読書ができる
上記のサービスはスマホやタブレットで書籍を読む、音として聴くことができます。
卒論に必要な書籍も読めるので、図書館で貸し出し中の本も見つけられるかも!

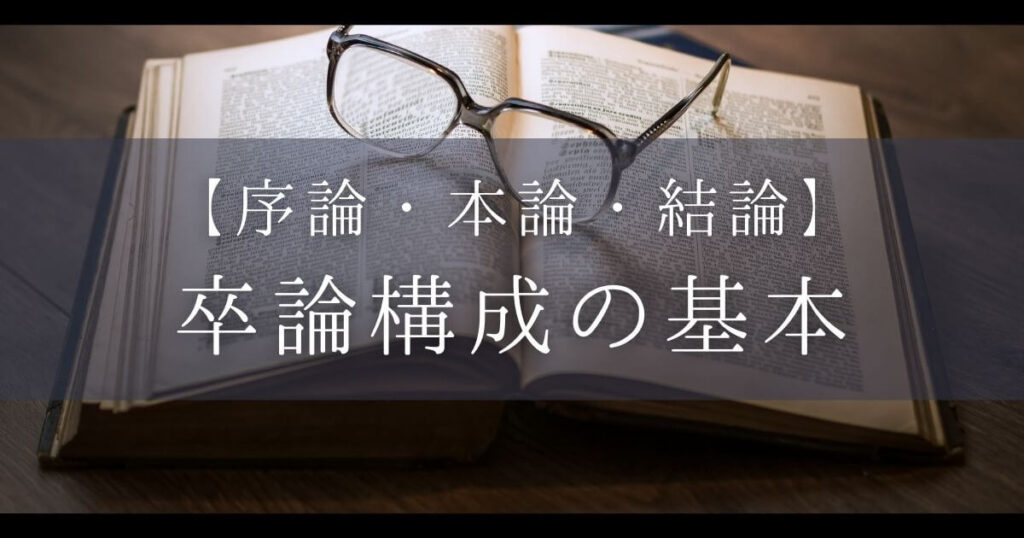
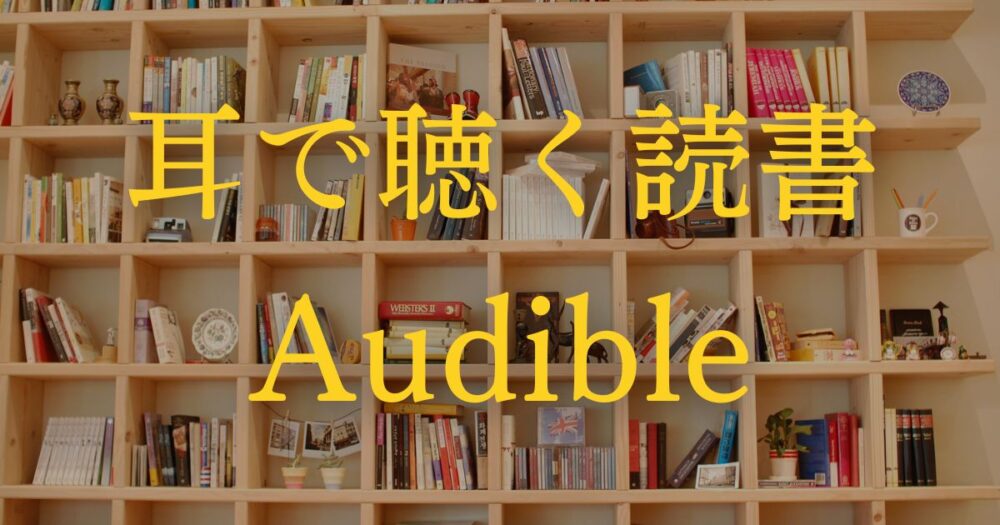
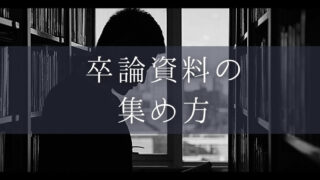
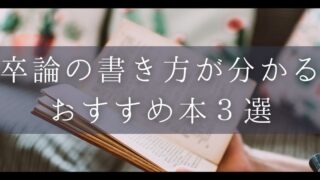
✓文系4年制大学卒
✓文系大学からIT企業に就職
✓現在フリーランス
就活情報を中心にブログ投稿をしています。
ライティング依頼・レビュー依頼のご相談はお問合せフォームまで。